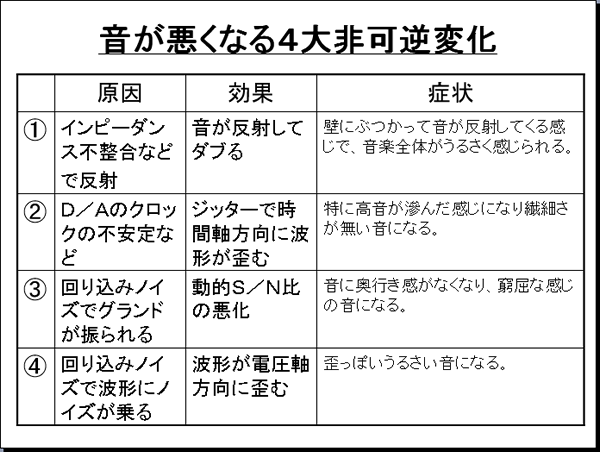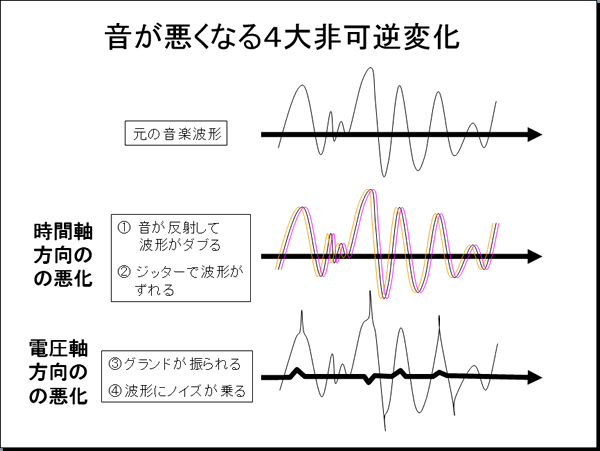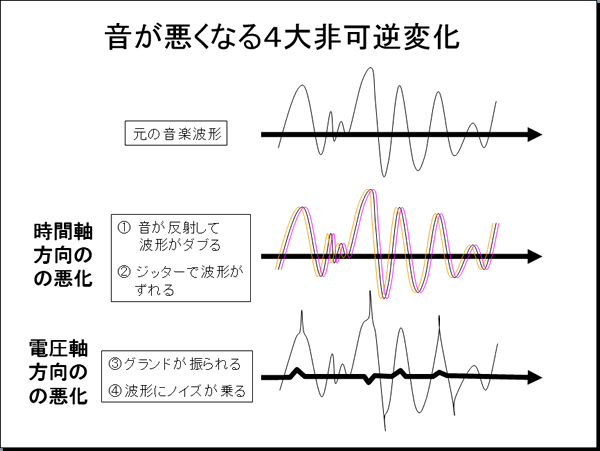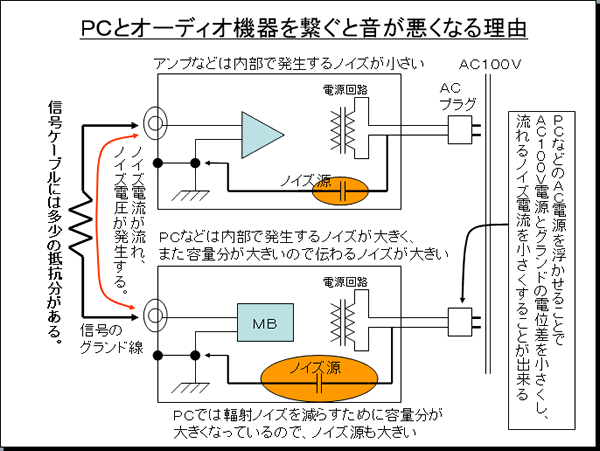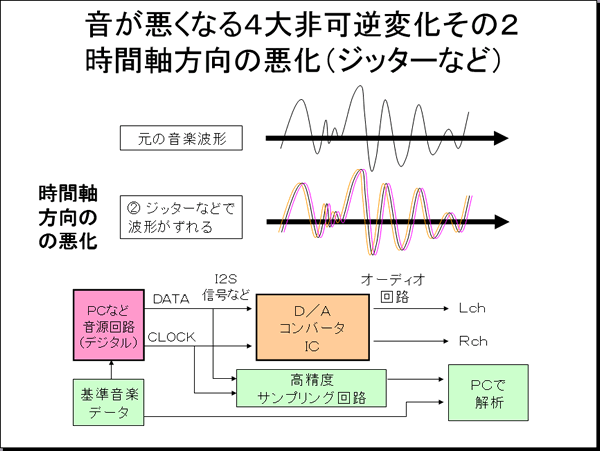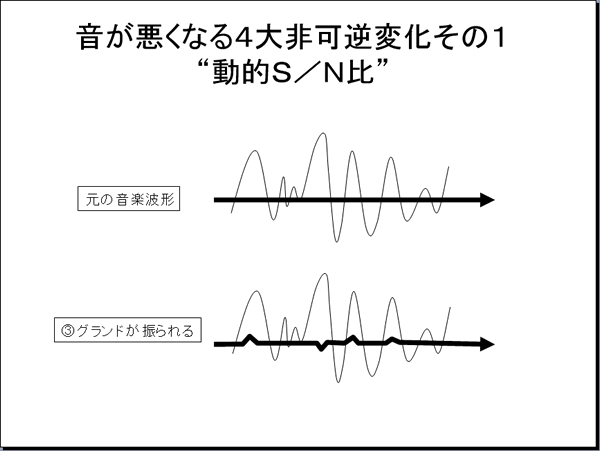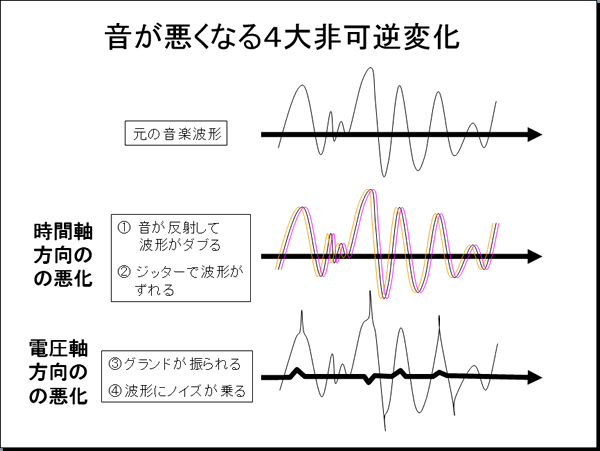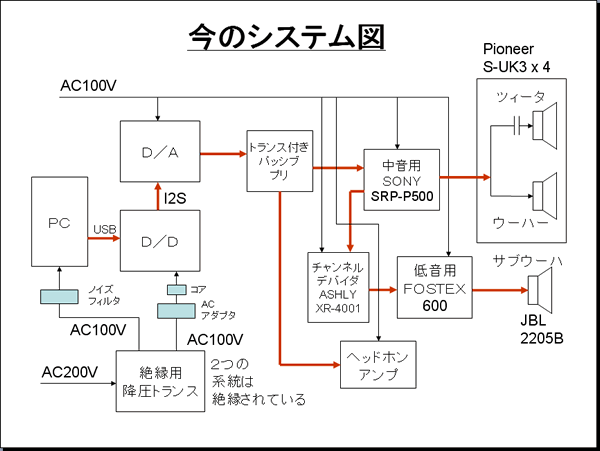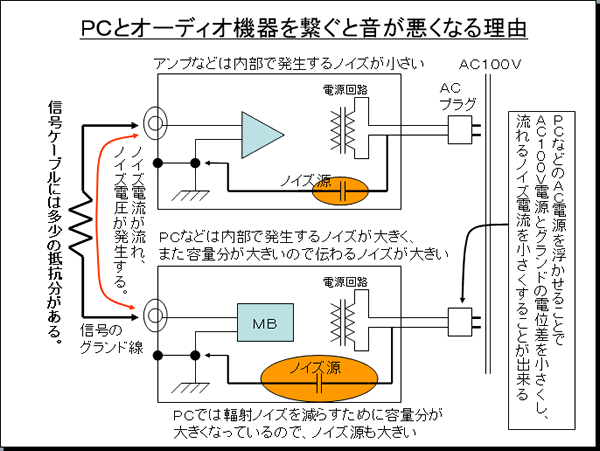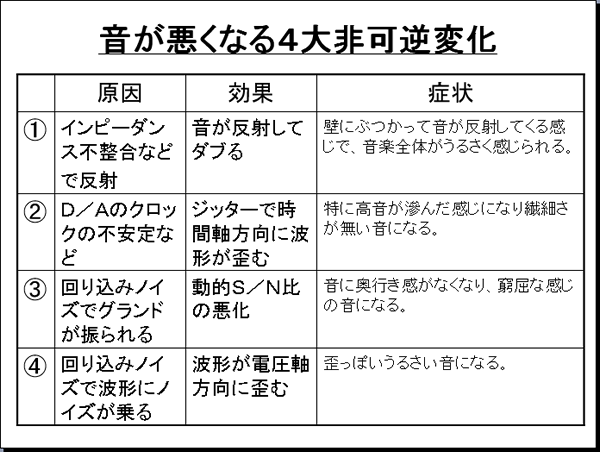
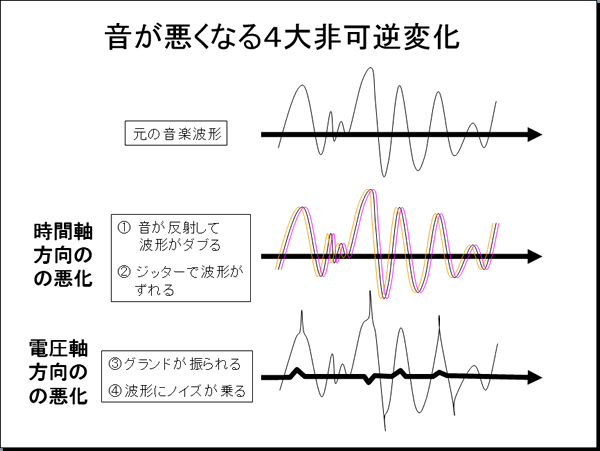
音が悪くなる4大非可逆変化について、原因と効果が混じっていたので整理した。
オーディオショーなど見に行っても、多くの展示物がこれらのどれかの悪さが聞こえる場合が多い。さすがに大きなブースの物はこれらの悪さを感じない場合が多いが、小さなブースの音は大抵上記のどれかが当てはまる場合が多い。
耳が慣れてくると音を聞くとどの悪さが入っているか判るようになるから不思議だ。
- 2011/09/27(火) 15:45:08|
- 音の比較/技術解説
-
| トラックバック:0
-
| コメント:0
”音が悪くなる4大非可逆変化”の3番目は、回り込みノイズだ。これもオーディオ信号のグランドを揺らし、動的S/N比を悪化させる要因の一つだ。
前にも書いたけれど、特にPCなどノイズ発生が大きい機器を音源として使う場合、電源の回りこみノイズはきちんと対策しないといけない。下の絵で言うと③④の原因となる。最近これを徹底的に対策したらスピーカーから出る音がすごくよくなった。ヘッドホンよりスピーカーの方が線が色々繋がっているから影響を受けやすいのではないかと推測する。この問題があると、音が濁る(ノイズでしょう)のと同時に音に伸びやかさが無く窮屈な感じがする。
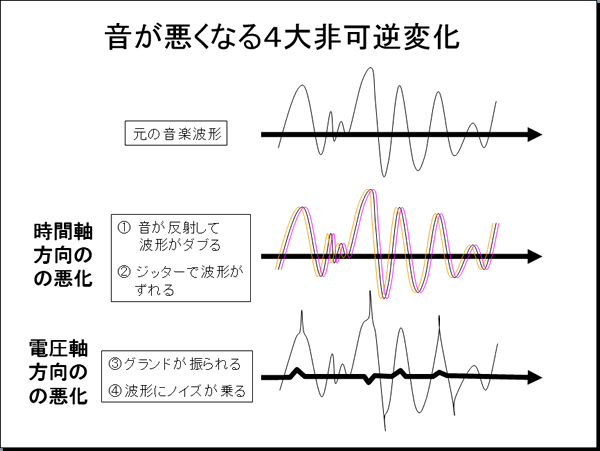
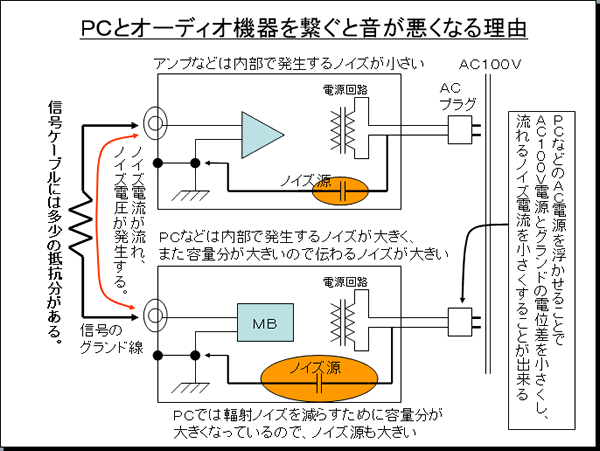
さてこれも原理的には理解できたし、実験でも良くなるのはわかった。だけどこれも測定することは出来ないんですかねー?この回り込みノイズの影響度を測る測定器があれば、改善もしやすいのにねー。何で測れないのか不思議だ。。。オーディオ信号のグランドとPCなどノイズ源のAC入力との間の絶縁度を測ればいいんだから、出来そうな気がするけどねー。。。
- 2011/09/22(木) 14:17:08|
- 音の比較/技術解説
-
| トラックバック:0
-
| コメント:0
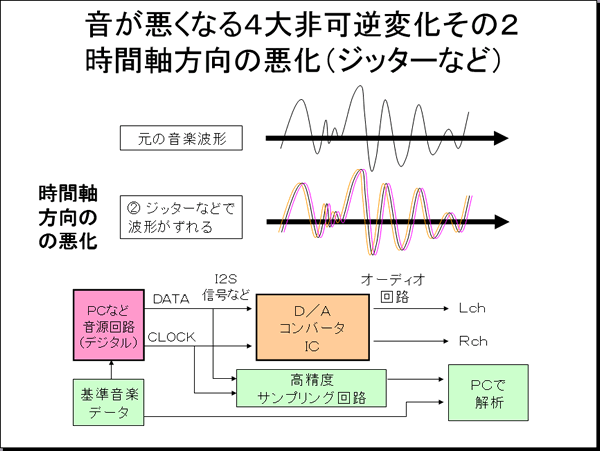
デジタルオーディオの音の悪化の原因としてジッターが取りざたされている。そのとうりだと思うが、何でそれを計らないのか? 上図の緑色の部分の回路で、
ジッター率 (クロックやデータが基準位置よりどれだけずれているか)
データ欠損率 (データがあるべき時に無い確率:D/Dコンバーターの性能を現す)
などを計れば、デジタルオーディオの音の良し悪しは一発でわかるのではないか?
I2Sの信号なんて高々数十MHz位だし、測定器なのだからいくら高くてもかまわなければ、今の技術なら実現できるでしょう。。。(いまどきのCPUのクロックはGHzオーダーですからねー。。。)
デジタルオーディオのメーカーは、何でこういう測定データを公表しないの?
本当に音を良くしようとする気があるのかなー? 私には理解できない。。。
- 2011/09/19(月) 23:33:14|
- 音の比較/技術解説
-
| トラックバック:0
-
| コメント:0
デジタルオーディオをひととうりいじくりまわして、かなり満足のいく音が出るようになって今思うのは、結局オーディオの音の良し悪しはかなりの部分がアナログ部分に依存していて、デジタルの部分はいかにそれを邪魔しないようにするか、つまりアナログ信号の精度に影響を与えないようにきちんとデジタル信号が渡され、アナログ回路の邪魔をしないようにノイズなどの対策がしてあるかがとても大事であるという事。
さてそう思うと、数十年前のアナログレコードの時代からオーディオ技術の本質は全く進化していないということが判る。ビニールのレコード盤に記録したアナログ信号の方が、下手なデジタルオーディオよりよほど良く聞こえるというのがなんとも不思議だ。
オーディオ業界は、CDだ、SACDだ、ネットワークオーディオだ、なんだかんだと流行り物を追いかけるけど、本質的なオーディオ技術はブラックボックスのままで何も進化していない。
その方がいかに自社の製品が凄いかを能書きだけで語れるオーディオマーケッティングには都合がいいんでしょうけれど、なんだか悲しいなー。
僕はオーディオが好きだからオーディオが楽しめるものであって欲しいけれど、そんなオカルトじみたマーケッティング戦略に乗せられるのはマッピラごめんだね。もっと本質的な進化が出来ないんでしょうかねー。まあ、そんなことやってもメーカーは儲からないからねー。。。こんなことをマジに考える方が馬鹿なんでしょうね。
- 2011/09/19(月) 00:00:14|
- ポリシー
-
| トラックバック:0
-
| コメント:0
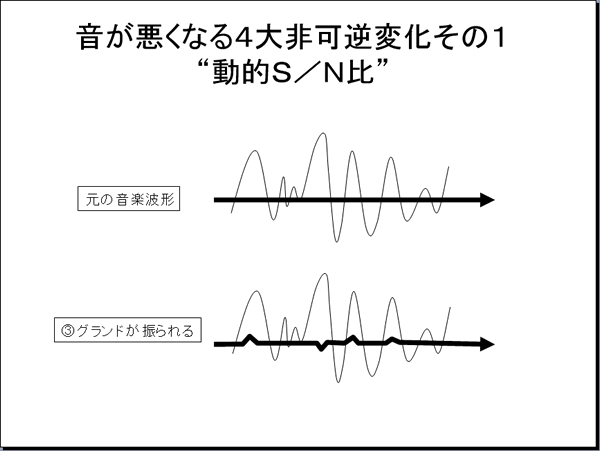
オーディオほどお金が無駄にかかる趣味はないと思う。車なら1000万円出せば世界的に見て優秀な車が買える。カメラなら100万円も出せば凄い機材が買える。パソコンだって100万円出せば凄い機材が買える。でもオーディオは数百万円出しても自分の家で良い音が出るとは限らない。こんな変な趣味はない。数十万円出したらそれなりの音で鳴って欲しい。購入したら家にサービスマンが来て良い音で鳴るようにセッティングしてくれるサービスも有ってほしい。何故そういうサービスが無いのか?要するに良い音で鳴らす自信がないのだ。こんなことでよいのだろうか?何故そうなっているかというと客観的に音の良し悪しを図る術がないからだ。だが本当にそうなのか?きちんと計ろうとしていないだけではないのか?
オーディオの音を悪くする原因は大きく分けると4つかなと思うが、その一つ目にこれを挙げたい。
普通にS/N比というとオーディオの出力信号の大きさに対して、無信号時のノイズの大きさを計って、それぞれを入力信号レベルに換算し、その比率をdBで表したもの。パワーアンプなどでは100dBを超える物がほとんどで、これが良いから音が良いという尺度には全くならない。100dBというのはオーディオ信号に対してノイズの大きさが10万分の1ということだ。
実際問題、こんな方法で計った100dBなんて数字に意味があるんだろうか? アンプの内部の基板上のグランド信号は上図のようにオーディオ信号にあわせて振られていて、アンプの設計をしている方ならその大きさが10mVくらいはあることが簡単に想像できる。
100Wのアンプで考えると電圧出力は30Vくらいだから30Vに対して10mVグランドが触れていたら、信号に対するノイズの比率は3000分の1。
これって、わずか70dBくらい。これこそ本当のS/N比ではないか?(動的S/N比と呼ぶべきでしょう)
こういう”動的なS/N比”ではなく、無信号時のノイズの大きさを測って計算する”静的なS/N比”に意味があるんだろうか?
なんで動的S/N比を計らないのだろう? ”信号があるときのグランドの振れなんて計りにくい” というのが言い訳かもしれないけど、こういうことをほったらかしておくからオーディオが何十年経ってもきちんと進化しないんじゃないの??
- 2011/09/18(日) 18:19:53|
- 音の比較/技術解説
-
| トラックバック:0
-
| コメント:0
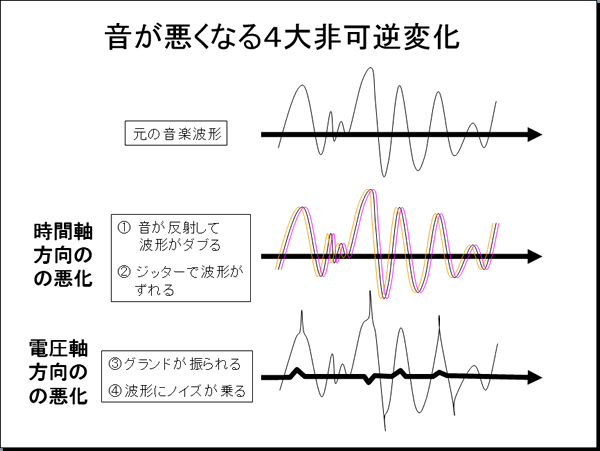
音が悪くなる4大非可逆変化を図にすると上のようになると考える。これらは一度変化してしまうともとに戻すことは出来ない。”オーディオ機器の個性”とは明らかに違う変化だ。
①は音がうるさく感じられるようになったり、ボーカルの定位が悪くなったりする
②は特に高音が荒い音になり、うるさくなり繊細さがなくなる
③は音楽全体に雲がかかったようになり、窮屈な感じの音になる
④はキンキンしたような音になる
さて問題は、これらの変化のほとんどが機器のスペックには現れず、オーディオ機器のユーザーが自身の耳以外では知ることが出来ないことだ。客観的に知るのが難しく、自分の耳を鍛える以外に知る術がない。(本当に測定できないのか、わざとやらないのかは私は知らない。)
お金持ちの皆さんは、このために高級なオーディオ機器に大金を払っているともいえる。
私は払いたくないねー。。。客観的に知れるんなら良いけどねー。。。
- 2011/09/11(日) 12:28:57|
- 音の比較/技術解説
-
| トラックバック:0
-
| コメント:0

最近思うんだけど、オーディオ機器を通ると音は多かれ少なかれ変化するけど、どれは音の個性でどれは音の悪化なのか、その差は微妙な感じがするよね。(写真のKRELL KSA-80Bは音を妖艶にするといわれている)
私が思うに、
音の個性 = 可逆な音の変化
音の悪化 = 非可逆な音の変化
なのではないだろうか?
周波数特性の変化やインパルス特性、アンプのリニアリティーによる音の変化などは原理的には元に戻すことが出来るけど、信号の反射(音のリピート)や時間軸方向の位置のずれ(ジッター)、ノイズで加わった波形の変化は元に戻すことは不可能だ。
人間の耳はそういった非可逆な音の変化は音が悪くなったと感じるのだと思う。
私は信号の反射やジッターなど時間軸のずれは音がうるさくなったと感じ、ノイズが加わって波形が変わると音が濁ったように感じる。
(ここで言うノイズは、シャーというノイズばかりではなく、グランドの振れも含む。)
次回は、広義の "ノイズ" とS/N比について考えてみたい。
- 2011/09/11(日) 00:22:06|
- 音の比較/技術解説
-
| トラックバック:0
-
| コメント:0

スピーカーの改良方法を思いついてやってみた。S-UK3はバスレフだから結構低音まできちんと出してくれるが、我が家ではスーパーウーハーがあるからそんなに低音はいらないし、バスレフだとどうしても低音がゆるくなるから、全体にモワッとした音になっていることに気がついて、バスレフのダクトを塞いでみた。
思ったとうり低音のもたつきがなくなり、その分エネルギーが中音寄りになり、よりはっきりした中音が出るようになった。まだ若干は大人しい感じではあるが、満足できる帯域バランスになった。デジタル回路のAC絶縁をきちんととってグランドを安定させたのもスピーカーの音にかなり影響したようで、とてもきれいなホールトーンや奥行き感を再生してくれるようになった。いままでかすれたような感じでつまらない音だったボーカルやサックスも楽しめるようになった。ボリュームを上げても全くうるさくないし、隣の部屋で聞いても良い音バランスで聞けるようになった。ソフトドームの音とは思えないようなドラムのアタックも再現できている。シンバルの音も美しい。
やっと、”昔のホーンスピーカーが懐かしい”という言葉を吐かなくて良い様になった。

もともと、S-UK3はイギリス人のデザイナーの設計なので、いわゆるヨーロッパトーンだから若干は大人しめなのは個性だから仕方ない。それを楽しんでいこうと思う。
これでやっとスピーカーも含めたシステム全体の音を人様に聞かせられるレベルになったなー。
- 2011/09/09(金) 23:23:17|
- スピーカー
-
| トラックバック:0
-
| コメント:0
以前、どなたかから、”どんなPCがPCオーディオに向いているのか?”と聞かれ困ってしまったことがある。
どんなっていわれてもそう簡単にこれが良いですなんていえるはずがない。そもそもPCから出るノイズにも色々在る。一言では言い表せない。
PCから出るノイズは、内部のCPUやメモリー、高速バス、スイッチング電源が高周波で動作することにより発生する。そのノイズを分類すると、
(1)内部の基板の信号(特にグランド)が振られることにより、信号を通じて電磁波として輻射されるノイズ
(2)内部の基板の信号(特にグランド)が振られることにより、外に出る信号(GND)がノイジーになる
(3)内部の基板のノイズやスイッチング電源のノイズが、電源のACラインに乗り、電源が容量成分で
グランドと繋がれていることで、結果的にグランドラインが振られる
PCのノイズといってもこれらのノイズの集合体だから、そう簡単にどのPCが良いなんて簡単にはいえない。
前の記事で書いた対策(ACラインの絶縁)は、(3)に対する対策だ。
その対策には、こんな手もある。
 NIPRONの絶縁電源
NIPRONの絶縁電源ちょっと特殊なので、あまりお勧めしませんが。。。単純に絶縁トランスを入れたほうが良いかもね。。。
(2)については、PCの内部設計の良し悪しによってしまう。PCの設計をしたことがある方ならお分かりと思うが、回路設計や基板設計の良し悪しで基板の信号へのノイズの乗り方は大きく違う。信号パターンの引き回しやノイズを抑えるように信号にダンピング抵抗を入れるなどにも影響を受ける。基板のグランドパターンの銅箔の厚さにも影響を受ける。だから正直、どのPCが良いなんて質問はナンセンスだ。使ってみるしか知るすべがない。。。定性的には比較的遅いCPUを使ったノートPCの方が良いのかとも思われるが、本当だろうか?
(1)については、まともなPCならEMIの対策が入っているから通常はあまり影響がないのではないかなー?もちろん他のオーディオ機器とある程度はなして配置する必要は在ると思うが。 また、不思議なもので、良く設計されたPCは(2)も(1)も特性が良いことが多い。基本設計が良くないと(1)で苦労するんだよねー。。。苦笑いする方がたくさんいると思うなー。。。

さて、
PCオーディオに関して言うと、通常は(3)の対策と(2)の対策が重要なのだけれど、(3)の対策は、AC電源をトランスで絶縁するか、ノートPCで電池駆動にすれば解決できる。しかし、(2)の対策はPC内部の設計しだいだから実際使ってみて比較するしか手がない。 さて(2)をどうやって判断するかが難しいね。こういう事を書いてある記事は見たことないねー。。。
PCオーディオにはノートPCが良いといわれているようだけれど、果たしてどういう観点でそう結論しているのか私にはさっぱりわからない。。。(3)の対策をせずにデスクトップとノートを比較するのはルール違反だと思う。(3)の対策をすれば我が家のデスクトップは十分音が良いように感じる。
ノイズ対策の話で、これら3つのノイズを分類して考えていない記事を見たらインチキだと思ったほうが良いですよ。
- 2011/09/09(金) 00:02:06|
- 電源回路/アイソレーション
-
| トラックバック:0
-
| コメント:0
PCやD/Dコンバーターなどスイッチング電源を使った機器ののAC電源をきちんと絶縁する効果は絶大であることが今回わかったけれど、まさかこんなに違うとは思っていなかった。薄い雲がかかっていたのがとれてピーカンの青空になった感じ。音がのびのびしている。
よく考えればわかるのだけれど、アナログ信号のグランドは色々な機器間を長い距離繋がるから信号がノイズで汚れやすく、それを汚さないようにすれば音が良くなるのは当たり前だ。グランドをいかにノイズから守るかがPCオーディオの真髄の一つだと判った。
そのためにはノイズ電流を外部からグランドに流さないように注意すること。そしてPCなどはノイズを大変出しやすい機器であることを理解し、それの対策をすることは他の何にも増して重要だ。電源ケーブルなどに凝るよりずっと大事だと思う。
- 2011/09/08(木) 00:47:17|
- 電源回路/アイソレーション
-
| トラックバック:0
-
| コメント:0
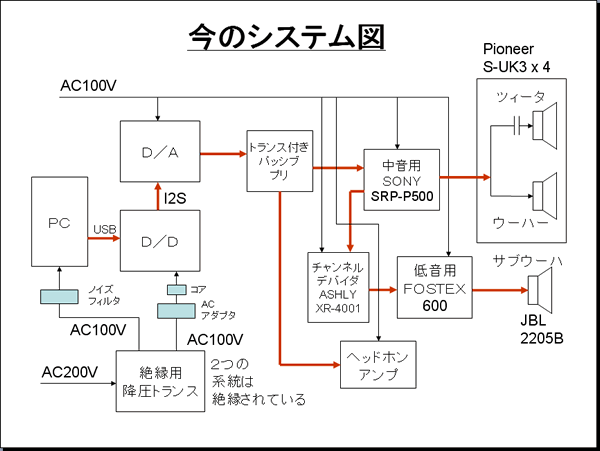
昨日の絶縁に関する考察に従って、D/Dコンバーターの電源を絶縁し、D/Aコンバーターの電源は普通のAC100Vから取るように変えた。D/Aの電源はスイッチングではなく普通のシリーズレギュレーターだから電源回路のトランスで十分絶縁されているから、これでよいはずだという考え。
この方がはるかに良くなった。音がよりクリアになり、音の伸びやかさは上なのに全くうるさくない聞きやすい音。お酒にたとえるなら吟醸酒の味わいだ。理論と実際が合致した時ほど気持ち良いことは無い。うれしい!
これで電源周りも一段落かな。PCオーディオを始めてから電源の取り方とグランドについて不可思議な点や疑問な点が在ったのだが、それが無くなった気がする。
この電源の取り方はPCオーディオでは何より大事だと思う。シンプルで見やすい回路になったときは、より良くなっているのは間違いないね!
みなさんあまり気にしていないようだけど、クロックを高精度化する前にこれはぜひやって欲しいなー。内臓クロックの精度を悪化させる大きな原因だからねー。
- 2011/09/06(火) 00:13:00|
- 電源回路/アイソレーション
-
| トラックバック:0
-
| コメント:3
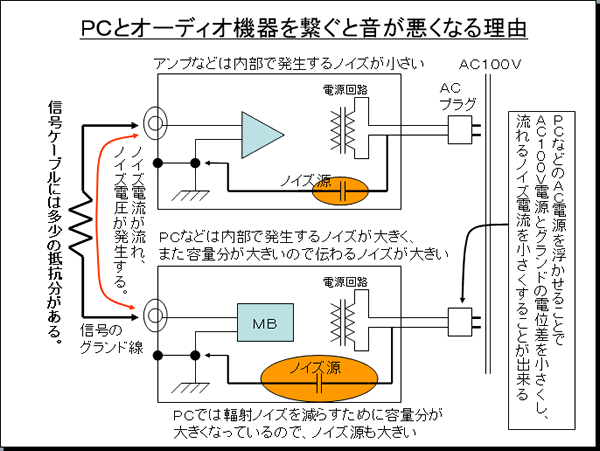
かないまるさんのページに詳しく書いてありますが、この方が多少わかりやすいかと思い、絵を描いてみました。
そもそもの問題点はそれぞれの機器に信号線(グランド)とAC電源線が繋がっていることです。そこに電位差が生じてノイズの元になります。機器の電源回路は内部のトランスで絶縁されていますから、機器の信号グランドとACラインの間にはかなりの電位差があり、ACラインは機器側の信号グランドから見るとフワフワした状態です。(日によってノイズの出方が違う場合がありますが、それはこのフワフワの程度が違うからです)
ACラインがトランスで100%絶縁されていれば問題ないのですが、PCにはかなり大きな輻射対策のコンデンサーも入っていますので(かないまるさんによると10000PF程度だそうです。)、その間に飛びつきノイズが発生します。これがオーディオ信号線のグランドに流れオーディオの音を悪くします。
これを完全に無くすためにはPCのACラインに絶縁トランスを入れます。いわばPCのACラインを二重絶縁にして完全な ”フワフワ状態" にしてやります。完全なフワフワ状態になれば、機器のACラインと機器の信号グランドとの電位差はなくなり(コンデンサーでショートされているので)ノイズ電流が流れることはありません。これによりほぼ飛びつきノイズを無くせます。
オーディオ機器を電池駆動にすると音が良くなるのは、電池が電源としてのインピーダンスが低いせいもありますが、このACからのノイズの回り込みを無くせるからです。(ACラインがありませんから信号グランドがACラインから引っ張られてノイズを発生することもありません)ですので比較的インピーダンスの高いマンガン電池でも音が良くなるのです。
図ではPCとアンプですが、D/AコンバータなどをPCと同じACラインに繋いだ場合は、その内部グランドがACラインからのノイズで振られ、内部のアナログ回路もノイジーになりますし、さらにクロック回路にジッターなどを発生させるので、時間軸的にも音が悪くなります。
PCなどのノイズ源の大きい機器のAC電源を絶縁して浮かせた方が良い理由をご理解いただけると幸いです。私はこれを理解するのに随分時間がかかってしまったので、ご参考までに。
詳しくは下記をご参照ください。
かないまるさんの絶縁の説明これらを理解するといくつかのことがわかってきます。
(1)アナログ系のアンプなどのAC電源を絶縁する必要は無い(へたに絶縁トランスを入れると音が悪い)
(2)信号ケーブルは太くてインピーダンスの低い物を短く使うのがよい。どこか1箇所グランドの基準を作って
(プリアンプになるのでしょうね)色々な機器をそこに繋ぐのがよい。
(3)PCは絶縁トランス無しで使うなら、ノートブックを電池駆動で使った方がよい
(これは間違いだった。ノートPCは内部にスイッチング電源を持っているからノイズ源を抱えている)
(4)PCやD/DコンバーターのACアダプタなどスイッチング電源を使った機器は
1台1台別個に絶縁する必要がある。(うーん頭が痛い)
(5)絶縁無しで使っていると、日によってノイズ量が変わるのが理解できる
(6)オーディオ機器を電池駆動にすると音が良くなる理由は二つあって、
ひとつは内部抵抗の低い電池を使うと電圧変動が少ないから(パワーアンプなど)
もうひとつはACラインからのノイズの飛びつきがなくなるから(内部抵抗の高い電池でもOK)
(7)D/DコンバーターのACアダプタから来るDC9Vラインが
線が細くてノイズに弱いのが理解できる
- 2011/09/04(日) 02:19:36|
- 電源回路/アイソレーション
-
| トラックバック:0
-
| コメント:0