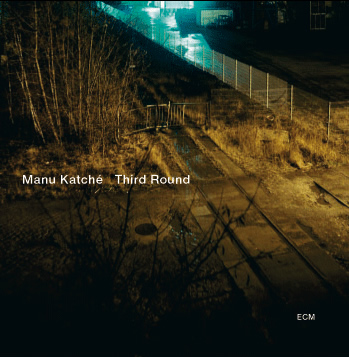中音ホーンに続いて高音ホーン(JBL:2404H)をPeaveyで鳴らしたらどうなるかやってみた。CS800Sはかなりいい感じではあるが、SONYの勝ちであった。CS800Xで鳴らすと音が暴れてしまう感じ。ヘッドホン駆動のときは多少の暴れ感が色気に感じなくもなかったが、ホーンスピーカを鳴らすと”暴れ”になってしまう。スピーカーはヘッドホンと異なり逆起電力がとてつもなく大きいのだろう。それを十分抑えられるアンプかどうかが重要になって来るようだ。
CS800Sはかなりいい感じ。ちょっとの差でSONYに席を譲った感じ。やはり奥行き感や繊細さが少し負けているように感じた。電源の違いのように感じる。
これもあくまでも我が家のホーンシステムを駆動した場合の話で、他のスピーカーだと評価が異なってくると思う。ホーンスピーカーはそれ自体が高能率で音が暴れやすいスピーカーなのだと思うので、それを十分に抑えることができるアンプが評価が良くなるのだと思う。
- 2010/04/18(日) 15:10:44|
- アンプ
-
| トラックバック:0
-
| コメント:0
【ご注意】以下のコメントは我が家の大型中音ホーンシステム(JBL:2420 + ALTEC:511B )を駆動した場合の比較ですので、一般のスピーカーを駆動した場合とは少し異なる評価内容だと思います。一般的なスピーカーの場合はヘッドホンをフルレンジで鳴らした場合の評価に近いと思われます。実際、我が家からお嫁に出て行ったJBLのアンプ:MPA600は新オーナーさん宅で大変高い評価をいただいています。
Peavey CS800Xで、我が家の中音ホーンを鳴らしてみた、同様にPeavey:CS800S JBL:MPX1200 KRELLのKSA-80Bと比較してみた。結果は、KRELLのKSA-80Bがダントツ良くて、次に良いのはCS800Sだった。CS800Sはうるささはまったく無かったが奥行き感がKSA-80Bにはかなわなかった。
不思議でしょうがないのだが、この中音ホーンはとても駆動が難しいらしく、一般的なアンプで鳴らすとすごくうるさい鳴り方になってしまう。たとえばサックスなどでいうと、サックスの音のすぐ後にどこかで反射してきた音が鳴っている感じで、とても耳障りな音になる。私の経験では、この反射音が出ないで鳴らせているのは、KRELLのKSA-80BとSONYのSRP-P500だったが、CS800Sが加わった。次に良いのがMPX1200。CS800Xはこのスピーカーとは相性が良くないようだ。
この中音ホーンシステムは、ホーンロードが思いっきりかかっているせいなのだろうが、すごくアンプを選ぶ。KRELLのKSA-80Bを手に入れることがなかったら私はとうの昔にこのスピーカーはあきらめていたと思う。中音の駆動力が良くないとまったく鳴らないスピーカーだ。はて、ここで言うスピーカーの駆動力とはいったい何なのだろうか?一般的にはダンピングファクターの値がそれをさすはずなのだが、それが高くても我が家の中音ホーンはうまく鳴らない場合が多い。KRELLのダンピングファクターが極端に良いわけでもない。CS800Sはダンピングファクターが良いのでダンピングファクターも効いているのかもしれないが。。。
まったくわけがわからない。だが、最近はヘッドホンを鳴らしてみると大体このスピーカーを駆動できるアンプかどうか想像がつくようになって来た。しっかりスピーカーを制動しているアンプの音がだんだんわかってきた。
こうなるとアンプとスピーカーの相性としか言いようがないですねー。。。
- 2010/04/18(日) 14:34:59|
- アンプ
-
| トラックバック:0
-
| コメント:0
前記事で ”ヘッドホンを鳴らすには、1000Wのアンプが必要だ”と書いたが、その理由としてアンプのノイズレベルとの関係を説明した。さらにもうひとつの理由を思いついた。
アンプがスピーカーやヘッドホンを鳴らす場合、少なくとも2M程度のケーブルがつき物だ。これは逆の見方をするとアンプに繋がったアンテナである。2Mのアンテナにどれほどノイズが乗ってくるかオシロスコープを繋いで見ればすぐわかる。このレベルは1mVをはるかに超えるだろう。
前記事で、CDのダイナミックレンジの音を再生するには最小の音を1mVで表現すると最大の音は64Vになることを説明した。つまり2Mのアンテナに1mVのノイズが乗ってくるなら、CDのダイナミックレンジを再生するにはアンプは64V以上出力できないと意味がないことになる。
もちろん、そんな電圧をかけ続けたらヘッドホンが破裂してしまいますけど、CDのダイナミックレンジを再生するにはかなりのピーク出力電圧がないとうまくいかないということの説明にはなると思う。
- 2010/04/14(水) 15:09:04|
- アンプ
-
| トラックバック:0
-
| コメント:0

PeaveyのCS800SとCS800Xを貸してくださる方がいらしたので、お借りして他のアンプとの視聴をしてみた。CS800SはCS800シリーズの最新機種でスイッチング電源。CS800Xはその前の機種だと思われ、通常のトランス式の電源。CS800Sは、Peaveyの最高傑作という呼び声もある。さてその結果はいかに。。。夜になるのを待ってヘッドホンで視聴。
CS800Sだが、音の出方は大変きれいで癖が無い。中音もきれい、高音もきれい、低音もまあまあで、Peaveyらしい熱い感じの音。だが残念ながら音の奥行き感、広がりがいまいちだった。やはり電源のせいか。。。
CS800Xはというと、これが素晴らしい。音の奥行きや広がりもばっちり。しかも中音、高音に癖が無く一点の曇りも無い感じ。ほんの少し荒い感じがあるかもしれないが、それが色気に感じられるくらいのものだ。クラシックのバイオリンもとても色気を感じる音。中高音が惚れ惚れする様な明瞭でありながら色気のある音。
MPX1200と較べるとMPX1200が音に厚みがあり少し低音寄りに重心がある感じ。CS800Xは少し高音寄りに重心がある感じ。どちらも甲乙付けがたい。味わいは違うが、両者とも一二を争う高音質アンプであることは間違いない。MPX1200を脅かすアンプの登場は初めて。中低音はMPX1200の勝ち、中高音はCS800Xの勝ちと言う感じか。どちらも音楽を楽しませてくれると言う点は共通している。
CS800Xはファン(ACファン)の音がうるさいのが難点。CS800Sはファンの音はまあまあ静か。
さてスピーカーを繋ぐとどうなるか。。。
- 2010/04/13(火) 23:58:22|
- アンプ
-
| トラックバック:0
-
| コメント:0
【補足】 動的S/N比についてはまったく同じ考えをONKYOさんが書いていました。
名前まで同じでびっくり。(記事を読んだ覚えはないのですけどね。)
ONKYOさんの記事アンプのS/N比は信号が何も無いときのノイズレベルと最大信号の大きさの比率をさしていると思うが、これに疑問を感じてきた。信号が無いときのノイズレベルに果たして意味があるのだろうか? 信号がガンガンに流れてるときにグランドレベルがどれぐらい振られてしまっているのかをノイズと考えた方が良いのではないだろうか? 要するに信号に対してそれを汚すような余分な動きはすべてノイズだから、それと信号の大きさの比率をS/N比というべきではないのだろうか? これはシャーと耳に聞こえるノイズではなく、音を汚すように聞こえるノイズだ。 そんなものは測定器で測り難いけど、それが本来のS/N比でそれが測れればもっと悪い値が出るだろうし、アンプの音との因果関係が数字ではっきり見れるように思う。もし10W出力のパワーアンプ(9V出力)で、信号が流れているときにグランドが10mV振られていたら、このS/N比は60dBしかない事になる。一般的なS/N比の100dBとはかけ離れた値になる。 これは "動的S/N比” と呼ぶのが良いと思う。
皆さん経験的に ”A級アンプは音がきれいだけれど音が詰まった感じがする" と言う経験がお在りだろうと思います。きっとこれはこの "動的S/N比”が、同じような回路構成のB級アンプに較べて悪い数字になるせいだと思う。A級だB級だという以前に、回路構成や基板設計の良し悪しに影響される(たとえば基板のグランドパターンが細かったらグランドレベルの変動は大きくなる)この"動的S/N比”が問題になるのだと思う。
- 2010/04/07(水) 23:13:51|
- システム解説
-
| トラックバック:0
-
| コメント:0
我が家では1000W級の大パワーアンプでヘッドホンを鳴らして楽しんでいる。そんなもの必要ないという人に考えてみていただきたい。ヘッドホンはスピーカーに較べて遮音性も良く、小さな音から大きな音まで大変リニアに再生してくれる。大きな音量を出す必要は無いが、ダイナミックレンジという観点ではスピーカーよりはるかにリニアに音を再生してくれる。それは皆さん同意いただけると思う。
さて、そのダイナミックレンジの大きな再生装置であるヘッドホンをうまく鳴らすのにどういったアンプが必要なのかを良く考えてみたい。
1000Wというと巨大に感じるが出力電圧で考えると高々90Vである。(負荷8オームで考えて)
一方、CDのダイナミックレンジは16ビットだから64000倍。つまり最低の音を1mVで表現したとすると、最大の音は64Vになる。これはほぼ1000W級アンプの出力電圧に近い。
アンプなど電子回路設計の立場で考えると1mVなんてノイズに埋もれてしまってアンプで再生できるようなレベルではない。(音が鳴ったときにはグランドレベルの変動だけでも10mVくらいのノイズは当たり前)
パワーアンプのS/N比はおよそ100dB これは信号とノイズの比が10万倍である事を示す。
これはCDのダイナミックレンジ(64000倍)に近い値。つまりCDの音をきちんと再生するには、パワーアンプ並みのS/N比が必要である。
では、出力が1Vしか出せないアンプが有ったとして100dBのS/N比を確保するにはノイズはどれくらいでなければならないか? 1mVの1/100である。これが単なるシャーと言うノイズのレベルなら実現可能かもしれないが、信号が流れているときのグランドレベルの振れと考えると、回路設計をした事のある方ならこんなの到底無理である事は自明だろう。
私は無音時のノイズレベルと音が出ているときの信号レベルを比較したS/N比の話をしているのではない。実際に音が出ているときにグランドレベルの変動などを含めて、信号レベルとノイズレベルの比率が100dB確保できるかどうかの話をしている
出力10Wのアンプは出力電圧は9V。これだと100dBのS/N比を確保するにはノイズレベルは1mVの1/10である必要がある。さてこれが本当に確保できているのだろうか?
大いに怪しい。では、アンプで100dBのダイナミックレンジを確保するにはどうしたらよいか? 最大出力値を上げるしかない。つまり100Vに近い大きな出力電圧を出せるアンプでないと、CDのダイナミックレンジは再生できない事になると思う。
そう考えると、CDを聞くためにヘッドホンを十分に鳴らすには、1000W級のアンプが必要という結論になりはしないだろうか? これはひとつの極端な計算例だが、いずれにせよ、小出力電圧のアンプではうまくヘッドホンは鳴らないというのは事実のように思う。
これは私の経験:”ヘッドホンを鳴らすにも大きなパワーのアンプの方が音がのびのび鳴っているように感じる” また ”A級アンプは音はきれいだけれど詰まった感じがする” に一致している。
- 2010/04/06(火) 13:50:06|
- アンプ
-
| トラックバック:0
-
| コメント:2
タワーレコードで素敵なジャズのCDを見つけた。音も良いし、音楽も最高。JacinthaのHere's to BenやShelby LynnのJust a Little Lovin' とならぶお気に入りになった。Manu Katcheはドラマーだが、リードアルバムにありがちな自分だけが目立つような録音にはなっておらず、サックス、ピアノ、ベースの音も最高。もちろんドラムは細心の録り方をしてあってディテールがすごくきれいな音で録れているけれど、それをさりげなく聞かせてくれるところがなんとも粋だ。
Manu Katche Third Round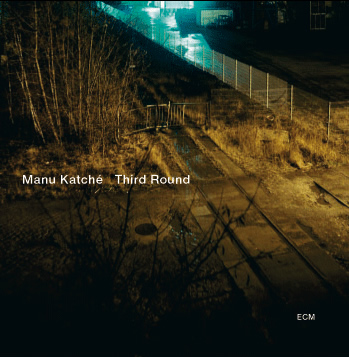
- 2010/04/05(月) 23:50:33|
- 音楽ソース
-
| トラックバック:0
-
| コメント:0
ある方の依頼で、1/5程度のアッテネーター入りのXLRケーブルを作った。我が家ではパッシブプリにトランスを仕込んでやはり1/5程度にしているので、その音比べをしてみた。結果はあまり変わらなかった。うれしいような困ったような。XLRコネクタの中に金属皮膜抵抗で分圧器を仕込んだだけの簡単な物だが結構いけてるようだ。コネクタ内に仕込むと結構いいのかな??
- 2010/04/05(月) 23:39:08|
- システム解説
-
| トラックバック:0
-
| コメント:0